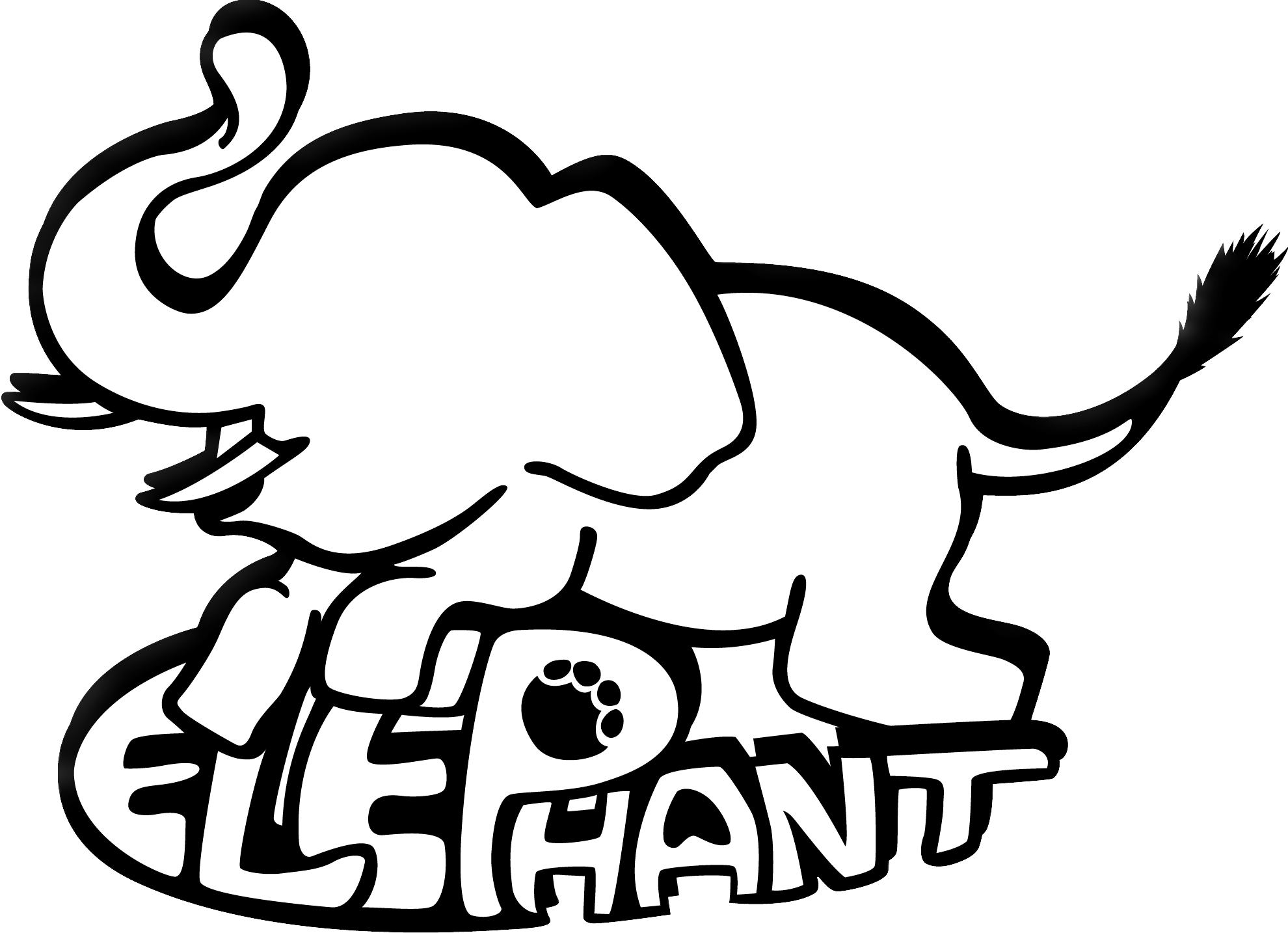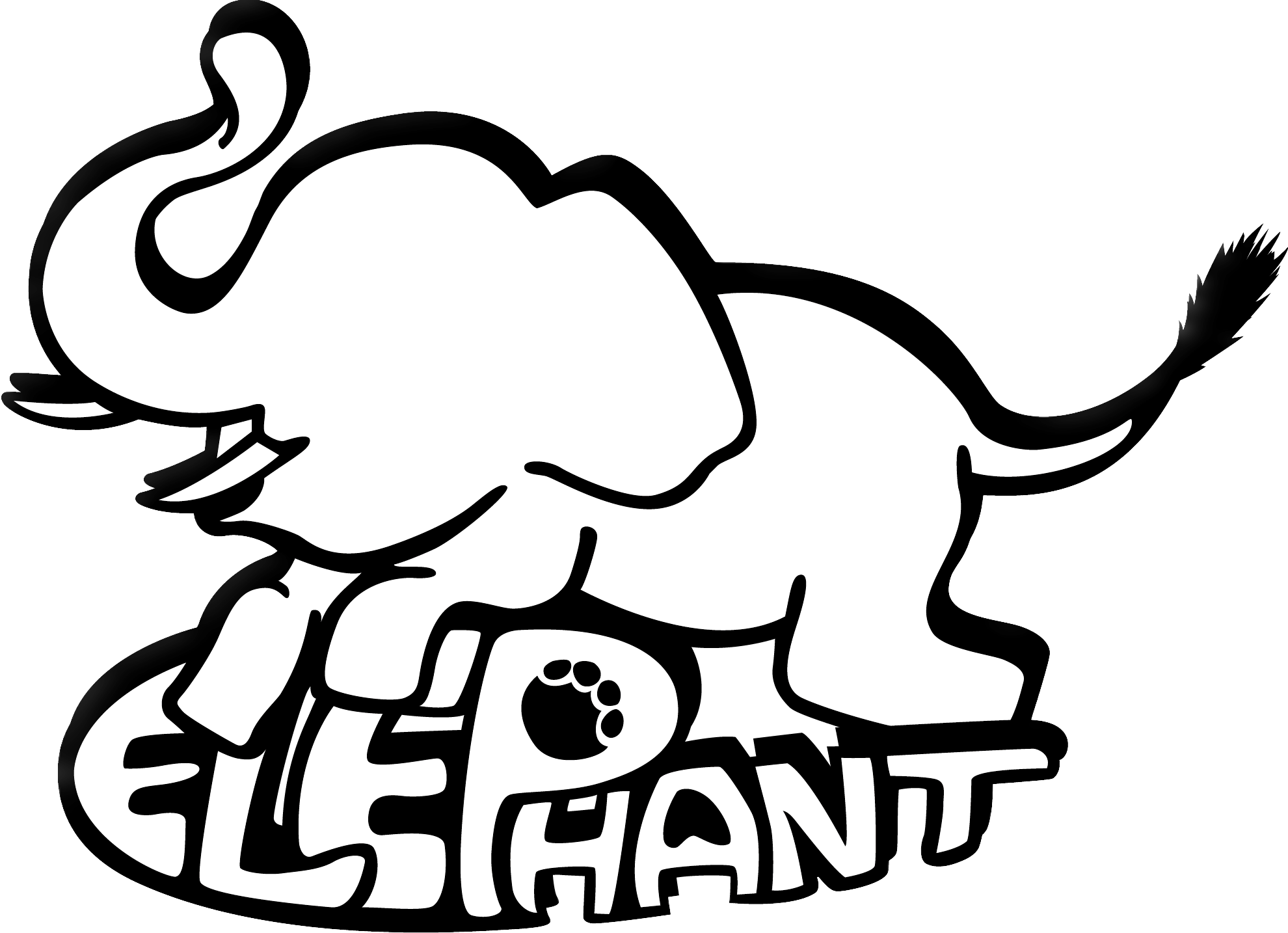2024/03/16 09:37
障害福祉を知り、理解するコラムSPOT LIGHT
二か月に一度ほど ELEPHANT が、施設、店舗、作業所などを取材して、そのリアルな声をお届けするページ。
その第一回目は・・・。
台東区今戸にある珈琲と焼き菓子のお店「IRODORI café」さんにお邪魔しました。

(「商品」きれいにディスプレイされた焼き菓子は、皆で協力して作っています。常連さんも、少しずつ増えてきました。)
IRODORI café ができた経緯を教えてください
もともと昭和60年福島県にて障がい者施設(さざなみ学園)を設立、平成23年より東京都台東区内にて障がい・高齢・子育てサポートを中心に運営してきました。
今回の障がい者施設「浅草みらいど」の開所にあたりましては、それまでのノウハウを活かしながら、”障がい者”という言葉が持つネガティブな印象を払拭し、「だれでも何度でもチャレンジできる場所」として、地域社会と共にイロドリを生むことができないかと、まず考えました。
「障がい者施設」の開所計画が公表されると、どうしても周囲から反対の声が上がってくる。
危険だとか、暴れる人がいるのでは? 近隣に脱走したらどうするのかとか。
反対の意見をする方の多くは、メディアなどで、興奮している当事者を支援者が制止する場面を強く記憶されていたり、日常生活で障がい当事者との接点がほぼないことによる認識不足から、ネガティブなイメージを持たれていたんですね。
そこで、理解を広めていくには、福祉の中にいる私たちしかいないと思い立ち、地域の人に開かれたカフェを開店することにしました。建物全体をほぼ全面ガラス張りにしたのにも、大きな意味があります。

(「ガラス張り」ガラス張り店舗にこだわって良かった、と坂様と松川様。外から中の様子が見えるのもさながら、作業スペースに日光がさしこんで、とても明るい気分で仕事ができます。)
中で作業している私たちの姿を見てもらうことで、地域と福祉施設の隔たりを取っ払い、自然に理解を深めてもらおうと・・・。
利用者さんに何か変化はありましたか?
就労継続支援 B 型は、どうしても賃金が低い。そこも改善したかったんです。親御さんの一番の心配は、利用者であるお子さんが将来自立して暮らしていけるのかどうかということ。
障害年金があったとしても、プラスアルファの収入がある程度なければ、グループホームに入るにしても、住み慣れた地域を離れ、家賃の安い地方へ転居しなくてはならない場合もあります。ですから、目標額を定めて仕事を割り振っていますね。
これまでは内職中心の作業所を運営していたので、作業収入を上げるにも限界がありました。
カフェは、一般のお客様に販売ができますから、やり方次第では大きな売上をあげることができます。
また、障がい者のショップの商品はクオリティも低く、安いというイメージがありますが、ここで扱うマフィンやパウンドケーキなど焼き菓子は世間の相場と見合う適正価格に設定、その分良い食材を使っておいしく仕上げています。
お客様もその味を気に入ってくださって、何度も来店してくださる人も増えました。そうするとコミュニケーションが生まれ、お互いの理解が深まっていく気がします。
最初はどうしても
「手伝ってあげている」
という感覚だったのが、コーヒーをいれられるようになり、それをお客様が、
「おいしい」とほめてくださると、自発的な気持ちが生まれ
「自分たちのカフェ」
という意識が芽ばえます。
それは私たちが願っていたことで、働く喜びを感じてほしいから、マフィンなどに入れる季節の食材を一緒に考えたり、アイディアを出しあったりして、より良いカフェを目指しています。
同じ人間ですよね。何も変わらない。
そう思っています。

(「外観」清潔なイメージの白い暖簾は、 NODD さんプロデュース。こだわりのロゴが目を引きます。)
嬉しかったエピソードなどあったら・・・。
カフェは、親御さんにとっても良い場所となっているんです。
なぜなら、いつでもお客さんとして足を運ぶことができる。お子さんの働きぶりを、ご自分の目で見てようやく安心するんですね。
「うちの子、本当に働けるのかしら? みんなに迷惑かけてないかしら?」
ずっと不安だった気持ちが、実際に見ることで変わっていき、
「すみません・・・」
という言葉が減っていく。ちゃんと笑顔で働いているんだな、と確かめられるからです。
障がい者のお子さんを持つ父母会のようなものもありますが、親の年齢層はまちまちで、その時代の価値観もありますから、なんでも相談できるとは限らない、中には誰にも言えずに一人で抱えてしまっている親御さんもいて。
そういう方たちがカフェに来て、ご自分もおいしいコーヒーでほっとひと息つけるのは良いことだし、軽い気持ちで悩みを話すこともできる。
私たちも仕事の合間に耳を傾けて、色々なアドバイスができるので、本当にオープンして良かったなと思っています。
IRODORI café の特徴とは何でしょう?
一番の特徴は、障がい者手帳の種類に関係なく、利用者さんを受け入れているということでしょうか。
通常就労支援施設や作業所は、手帳の種類によって受け入れる人たちが限られているところがほとんどです。
手帳には身体、知的、精神と種類がありますが、すべて受け入れることで、良い点がいくつもあります。それぞれ得意な作業が違うんです。
接客、クッキーの型抜き、セロテープ貼りなど、利用者さんができる範囲で作業することでお互いに補い合うというか。カフェの仕事だけでなく、画用紙を数え、ビニール袋に入れ、商品のシールを貼るなどの仕事も適材適所でお願いしています。
そこに共生・共存が生まれます。
もちろん最初はトラブルもあるけれど、少しずつ解決しながら良い形を目指していけていますね。
こだわっていることはありますか?
何より大切なのは利用者さんが快適に仕事に就けることです。私たちは、毎朝その日の利用者さんの気分を知るための「気持ちカード」というものを書いてもらっています。
スタッフはそれを見て、臨機応変にどんな作業をしてもらうか決めます。
まずは寄り添いつつ、必ずポジティブな言葉かけをするようにしています。それを根気よく続けていくことで、だんだんと変化が現れてくるんです。
たとえば、
「今日は朝から仕事をしたくない気分だった」
とだけ「気持ちカード」に書いていた人が、そのうちに、
「そんな気分だったけれど、スタッフさんにほめられて午後には仕事が楽しくなってきた」
というように前向きな気持ちでまとめられる、というような・・・。
私たちは、そういう「気持ちカード」を見ると本当に嬉しくなりますし、一緒にカフェを盛り上げていこう、と改めて思い、気持ちが引き締まるんです。
取材を終えて・・・
お二人のお話はとても具体的で、日々ふれあっているからこそのエピソードをたくさん紹介してくださいました。光景が目に浮かぶようです。
いつも前向きに考え行動する様子は、たくさんの見習うべき点があると思いました。
次回も濃いお話の続きをお届けいたします。お楽しみに・・・。